
葉山町観世流謡曲会では、毎月第2、3木曜日午後、図書館2階の和室で、研謡会、翠謡会というお稽古会を行なっている。加えて、春の会、浴衣会として研修会、そして葉山町文化祭では福祉文化会館大ホールで公演している。
3月27日、春の会を、図書館2階研修室(和室)で11時から16時まで開催した。
出席は、池田、井上、鈴木、大久保、小谷部、北邨、小谷部、後閑、高橋、高梨、堤、中川、掘内、浜野、掘内、宮内、山田、若林、若松さんの17名(男7女10)であった。
謡曲とは言え、趣味の会なので、足や腰が不自由であれば椅子を使い、服装も着物でも洋装でも謡うことが出来る。

番組は、今回は曲柄にこだわらす、シテを謡う人の希望にした。半蔀(シテ高梨)、隅田川(シテ小谷部)、草紙洗小町(シテ北邨)、藤戸(シテ大久保)であった。また、中川が仕舞(玉鬘キリ)を舞った。
謡曲は、観世流をみても200曲以上あり、今回の半蔀のように源氏物語から題材をとるなど、平家物語、伊勢物語など古典文学がお好きな方や箪笥に眠っている和服を着たいという方、お腹から声を出す、仕舞なら背筋を伸ばすなど、地道に続けていくので、健康を保つにもよい趣味と言える。
中川も謡いは65歳から、仕舞は70歳から能楽師浅見慈一先生に師事している。ご興味のある方は気軽にお稽古会を見学していただきたい。(ろくさん)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

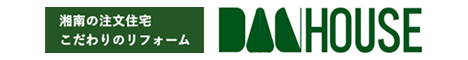
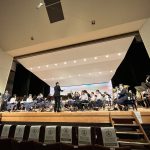





この記事へのコメントはありません。